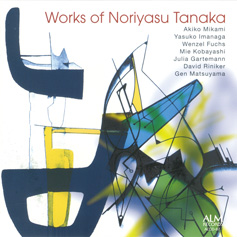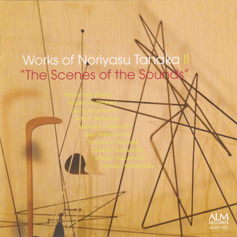マスターtoアーティスト
田中範康(たなか のりやす)
大学院音楽研究科 教授
広報企画部長
作曲家
- 1952年
- 東京生まれ
- 1971年
- 国立音楽大学附属高等学校 作曲専攻卒業
- 1975年
- 国立音楽大学 音楽学部 作曲科卒業
国立音楽大学 音楽学部 器楽科(オルガン専攻)学士入学 - 1977年
- 国立音楽大学 音楽学部 器楽科卒業
卒業後、作曲活動を開始、NHK-FM、アメリカ、韓国などの放送メディア、国内はもとより、ドイツ(ベルリンボン、ヴァッサーブルク)、オーストリア(ウィーン、ザルツブルク)、フランス(パリ)、北欧(コペンハーゲン、オスロ)、ベルギー(アントワープ、ルーベン)、アメリカ(ニューヨーク)、メキシコ(メキシコシティ、モレーリア)、韓国(ソウル、テグ、マサン)の音楽祭などで、作品が広く紹介されている。
1996年、2002年にオーストリアVienna Modern Mastersレーベルから、2枚の室内楽作品によるCDアルバム、国内ではALM RECORDSから作品集をリリース。最新作は、昨年11月発売「田中範康作品集II[音の情景]」
理性と情熱
音楽は、リズム、メロディ、ハーモニーの三要素から成り立つとされる。では、これらの要素の内、一つでも欠けてしまったら音楽と言えないのか? そんな疑問に対し、答えの模索を行っているのが「現代曲(現代音楽)」である。現代曲は、20世紀初頭に始まる。そのころクラシックの音楽界では、新作は発表されるものの、実際に聴かれたり演奏されるのは過去の作品ばかり。新しさを求めてはいるが、ワーグナー、マーラー、あたりでそれまでの音楽理論に立脚した音楽(調性音楽)は完成し、それらを打ち破るような革新的な表現は行き詰まりつつあった。クラシック音楽と言うと、何百年も前の古典のような気がするが、例えば、マーラーの交響曲5番が1901年、プッチーニの蝶々夫人が1904年、ホルストの惑星が1916年……、ちょうど今から100年前と、近代になって作られた作品である。これらの古典的なクラシック音楽の次の時代に現れたのが、音楽の三要素から外れた「無調」(現代曲)である。そして、その後、現在までの100年間、芸術音楽の分野では、年代ごとに扱う問題や音楽の在り方に微妙な差異はあるものの、現代曲(無調)の時代が続いているとされる。田中氏は、この流れの中にある作曲家であり、精力的な作曲活動を続けている。時として、混沌としていて難解とされる現代曲だが、その作曲者が考えることはどんなことなのだろう。
「今思えば、作曲のことを軽く考えていましたね。小学校6年の頃から簡単な作曲の理論のレッスンを受けていました。高校を受験する時に、その先生が『男だったら作曲なんかがいいのでは』と言ってくれて、後から思えば、それがきっかけの一つなんですよ」 音楽家志望であった母親の意向で3歳からバイオリンを始め、小学生時代はピアノ、中学生時代は吹奏楽にのめり込んだ。「通っていた中学には、合唱部はあったのですが僕は歌が好きじゃなくて。それで、7、8人の友人と吹奏楽をやろうよと始めて、3年生になる頃には40人くらいの編成になりました」 ブラスバンドでは、トランペットとユーフォニアムを担当する傍ら、編曲をこなし、まとめ役として指揮をする立場になっていた。「当時は楽器も足りなくて、ならばということで生徒会役員の友達と連れだって学区であった世田谷区長に『楽器を買って欲しい』と陳情しました。話題になって、買ってもらいましたよ(笑)」 部活では吹奏楽、個人ではピアノと音楽一色の中学時代を過ごし、音楽の道に進みたいと考え始めていたが、すんなりとはそう決まらなかった。「今のような時代じゃないですからね。親にも反対されましたよ。中学校の担任にも『精神的におかしい』と言われて、親も学校に呼び出される始末(笑)」 それでも、音楽をやりたい気持ちは変わらず、国立音楽大学附属高校 作曲専攻に進学する。ブラスバンドを編成し編曲を手がけ、区長に陳情する中学生となれば、非常に論理的な思考と情熱的な行動力を持つと言えるが、この一見、相反する2つの性質が田中氏に備わっているように思われる。
高校を経て、大学の作曲科に進学するが、作曲家としての道を目指すと同時に演奏者としての希望も捨てたわけではなかった。「大学に行ってピアノも専門的にやっていきたいとも思っていたのですが、パイプオルガンに興味が出てきたんですよ」 当時、パイプオルガンは非常に珍しく、教会に設置されているものを除けば、国内に数台しかないものだった。オルガンがやりたくて、ここでも情熱的に動いた。「ちょうどアメリカから帰っていらしたオルガンの先生がいて、その先生に電車の中で、教えてくださいと入門ですね。僕は、当時練習用のオルガンを持っていなかったので、先生に断られたのですが、すぐに買えるものではないので、足鍵盤を紙に書いてね、それで練習したものですよ(笑)」 作曲科を卒業後、オルガンを専攻するために学士入学をし、プレイヤーとしても研鑽に励んだ。しかし、ここで思わぬことが起こる。「オルガンに移って1年目の時に指を壊してしまったんです。親指が麻痺して動かなくなる......当時は様々な病院でみてもらいましたが結局原因が分かりませんでした。今の時代、医学が発達して、過度な練習や、指の使い方が悪いために起こる神経伝達の障害で、フォーカルジストニア(局所性ジストニア)という難病があるそうですが、それだったのかなと思う事も有ります」 フォーカルジストニアは現在でも治療の難しい病気の一つ。田中氏の場合、原因ははっきりしていないが、いずれにせよ、「指を強くしようと重りをつけてトレーニングをしたりしていましたからね。そういう無理な事をしたのが指をいためた原因だったのだと思います」
指を壊すことになってしまったのは、エモーショナルな行動が行き過ぎた結果と言えるが、顧みれば、論理的な思考と情熱的な行動が、ない交ぜに行き来している学生生活が浮かび上がってくる。そして、その構造は、田中氏の音楽に、そのまま現れているように思われる。「作曲というものは、基本がしっかりできていないと駄目ですね、建築みたいなもので、構造計算のしっかりできていない作品は、聴いていても作曲者の意図が伝わらないかと思います」
優れた抽象画には、裏打ちされたデッサンの技術があることを思い起こさせる。作品には、楽器間の緊張あるやりとりとエモーショナルなフレーズが行き来する。一見対立するように見える要素が、答えを模索するように響きそして溶け合う。調性音楽と無調、洋画と日本画、デジタルとアナログ......、すべてのアートの分野で起こっている問題を扱っていることに気付かされた。
3歳の時、近所に住むバイオリニスト(オーケストラのコンサートマスター)のところへ習いに行ったのが音楽との出会い。小学2年でピアノを習い始めるが、バイオリンからピアノへ変わる数ヶ月間だけが楽器に触れていなかった期間という。音楽と深く結びついた人生。
高校3年生の時のピアノ作品発表、ゲネプロ風景。「日本の音大生は、楽器の練習は一生懸命やるのですが、いろいろな音楽に関すること、例えば、作品の構造がどうなっているかだとか、さまざまな時代の文化背景から影響される解釈だとか、そういったことを自発的に考えてトレーニングするような勉強が不足していることを強く思いますね。応用力というのは、基本的な部分を学ばないといけないのですが、そういった部分の教育が全般に足りていないように思います」
ピアノソロのためのモノローグ曲集より<第1番>
出版社:マザーアース
2014年11月新刊。3冊目の楽譜出版
Chamber Music Vol.1 (1994)
Chamber Music Vol.2 (2002)
Works of Noriyasu Tanaka (2011)
The Scenes of the Sounds (2014)
「Sparkling in the Space Ⅰ(残照の時)」はエレクトロニクスを用いた曲。大学にサウンドメディアコースができた時から、エレクトロニクスをどうやって自分の音楽に融合させるかということを考えていましたが、それをコンセプトに本作品を作りました。