
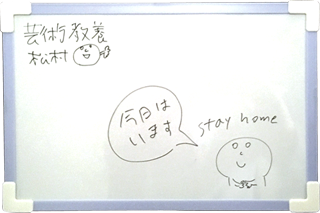
松村淳子
芸術教養領域 リベラルアーツコース 講師
フリーランスエデュケーター
学生時代に同級生の近藤令子とアートプログラムユニット「フジマツ」を結成。2006年、日用品を展示し、新たな視点から価値を問い直す「フジマツ美術館開館記念展覧会」を開催以来、現在まで数多くのアートプログラム、ワークショップを開催。

【プログラム・ワークショップ講師】
【フジマツでの活動】
研究室にお邪魔したのは6月1日、対面授業が再開された日である。キャンパスには学生の姿が見られ、ようやく学校らしさを取り戻しつつある。しかしながら、以前と同じように見えても、行き交う人の全員がマスクをしていたり、何となく距離感が違っていたり、世の中が変わってしまったことをことさらに感じさせる。真新しい研究室をたずねると、がらんどうの空間にラップトップPCがポツンとあるだけ。しつらえられた本棚は、ほぼ空で何も入っていない。4月から時間が止まってしまっていたようだ。それでも、迎えてくれた部屋の主は、変わってしまった世界に何か活力を与えてくれそうな、そんな明るい雰囲気だった。
「フリーランスでエデュケーターをやっています。アーティストではなく、アートとそれを受け取る人たちをどうつなぐか、そういうことをやってきました」 エデュケーターは、キュレーターともコーディネーターとも、もちろん作家とも異なる立場。美術教育にかかわる職業だと想像は付くが、聞けば、美術展などの来場者、観覧者たちに対して働きかけを行う認識だそう。むりやり日本語にすれば、美術教育普及担当者というところか。最近になり社会的にも認知され、ようやく市民権を得てきた職業である。「教育普及担当ですけど、教えるというよりは、ヒントをたくさん置いて、見た人に考えてもらったり、興味を持ってもらったりするきっかけを作るということをやっています」 本棚から取りだした小さなバッグ。2016年のあいちトリエンナーレで、実際に貸し出しされたものだという。開けてみると、色の付いた円盤、砂時計、作品の一部を写した写真やオノマトペのカードなど、さまざまなものが入っている。「これを持って、作品を見てもらうんです。円盤は回して止まったところの色が使われている作品を探してみる。写真はその作品を探してみる。砂時計は砂が落ちるまで3分かかるんですが、その間、じっくり鑑賞する。こんなふうに、作品を鑑賞するためのヒントや、新しいことに気が付くためのきっかけ作りをやってきました」 なるほど、観覧者の視線を作品のさまざまな場所へ誘導する仕掛けがたくさん用意されている。
「私は美術文化学科の3期生なんです。高校時代、生物の先生になりたかったんですけど、進路を決めるとき、これまで巡り合った先生たちみたいになれるかなと考えてみたら、到底自分にはなれそうにない(笑)。たまたま姉が名芸のデザイン科に通っていて、大学に美術文化学科というのがあり、向いているんじゃないかと言ってくれたんです。もともと絵を描くことは好きだったんですが、何かを表現するということよりもアウトプットされたものを見るのが好きで、これだと思いました」 美術文化学科は、作家や作品の背景について研究するコース。そこにアートプログラムとして人に作品を見せたり、体験させたりする活動が加わっている。そのきっかけについてうかがうと、恩師との出会いだった。「美術教育、幼児美術が専門の前田ちま子先生(名誉教授)がいらっしゃって、名古屋ボストン美術館でプログラムを行う課題がありました。その時期に開催される展覧会に合わせたもので、一般の入場者に対して行うものでした。その経験ですね。作品を調べ、自分で面白いと思ったことをお客さんに伝えて、その反応が返ってくる。ぜんぜん思うような反応でなかったり、ときには辛くて泣きそうになったり。それでも作家を研究しているだけでは得られない魅力を感じました。参加者によって、同じプログラムでもまったく違う着地点に辿り着いたりします。とにかくそのことが面白かったですね。先生はそんな機会をたくさん与えてくれました」。
学生時代には、恩師ともう1人、現在も共に活動を続ける友人(近藤令子)との出会いもあった。「4年生のときに“フジマツ”(近藤、松村の真ん中を取って、藤松=フジマツなのだそう)というユニットを組んだんですけど、彼女と一緒にアートプログラムを行い、自分たちだけでもプログラムがやれると実感できたことが嬉しかったですね。NHK教育テレビの『ハッチポッチステーション』という番組が好きで、その中にキュレーターを面白おかしく紹介するコントがあったんです。『日曜美術館』のパロディみたいな感じで。日用品を大袈裟に紹介するんですけど、それが面白いねと話してるうち、デュシャンのレディ・メイドにもつながるんじゃないかと、深夜のファミレスで2人で大いに盛り上がりました。それでできたのが最初のプログラムだったんですよ」(マルセル・デュシャン:既成のものをそのまま、あるいは若干手を加えただけのものをオブジェとして提示した「レディ・メイド」を数多く発表。作品「泉」が有名) さまざまなものを従来と異なった角度や新しい視点で見ることで新たな魅力を発見しようとする姿勢は、このときすでにできあがっている。
「ぜんぜん自分の知らなかった魅力的なことを知ったときや自分が思い込んでたことが違うと解ったとき、パッと目の前が明るくなったような、視界が開けたっていう感覚になります。たぶん、誰にでも経験のある感覚だと思いますが、私はプログラムをやっているとそういう気持ちになります。そんな感覚をみんなに抱いて欲しくてプログラムを作っているんですよ。パッと世界が拡がったようなあの気持ちを、一緒に味わいたいんですよ」。
発想の根底には、目の前にあることを楽しむことがあるようだ。深夜のファミレスでの雑談を見せられる形まで持っていくには苦労もあったと想像できるが、それを成し遂げ、アイデアを現在まで大事にしていることには敬服する。研究室の本棚は、やがてさまざまなもので埋められていくのであろう。どんなもので埋められていくのか。きっと楽しいものになるに違いない。

「フジマツ美術館 開館記念展覧会」(2006, 名古屋芸術大学)
在学中に行ったアートプログラムユニット フジマツの最初のプログラム。参加者に、日用品を作品として展示することに挑戦してもらった







あいちトリエンナーレ2019「アート・プレイグラウンド はなす TALK」
来場者が作品や体験の感想や考えたことなどを話して共有する場所(コーディネーターとして企画運営)

「ミラーニューロン・トレーニング」(2018,愛知県児童総合センター)
「ものまね細胞」と言われるミュラーニューロンに焦点をあてて、まねっこをする能力を鍛える複数のあそびのプログラムを実施。フジマツがリサーチしたミラーニューロン情報や参考資料も展示





「日用品美術館」(2014, 刈谷市美術館)
参加者が学芸員になり、身近にある日用品が美術作品だったら? という視点で見直し、展示、解説カード作成までを体験する