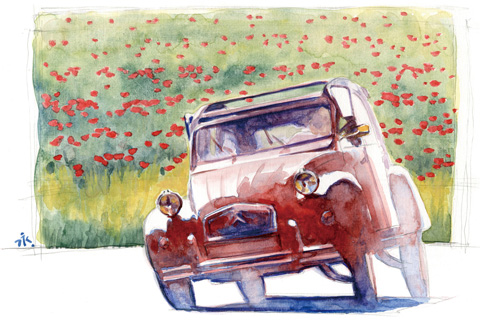アート&デザインセンター、イラスト展「ヨーロッパ自動車人生活」の会場で、お話を伺いました。永島讓二氏の美しいイラストは、カーグラフィック誌に掲載されたもののオリジナル作品。展示されるのは今回が初めての機会となります。
いっぺんに見てみたい(髙次)
この展覧会について教えて下さい。
片岡:カーデザインコースを立ち上げ、2年たち成果も出てきました。さらにもう一つ進めて、皆さんにカーデザインの良さをわかっていただきたい。名古屋芸術大学は、2020年に50周年を迎えますがこの展覧会は、そのプレイベントとして承認をいただいています。そういう背景があるのですが、それはそれとして、髙次さんに大学へ来てもらって4年目になります。一緒にいろいろ話をする中で、カーグラフィックに20年間連載している永島先生のコラム、あれのオリジナルを見たいねという話になりまして。
髙次:月刊誌なのでバラバラになってしまって、バックナンバーを掘り返したりとかするのも時間がかかるし、一度集めて、いっぺんに見てみたいというのが今回の企画の最初ですね。集めてみれば何かわかるかもしれない。世界観みたいなものが感じられるのではないかと、それが最初ですよね。
片岡:あれだけの連載をされて、でも、通り過ぎて行ってしまうのがあまりにももったいない。形にしなければいけないと思いますし、カーデザイナーの世界において永島譲二という偉大なデザイナーがやってきたことを形に残しておきたい。
永島:あんまり本気にしないように(照れ)。
片岡:いえいえ、本当にこれを残すことは自動車のデザイン界においてとても大事なことだと思ったんですね。髙次さんとそういう話をするうちに盛り上がって、今度、ヨーロッパへ行ってくるから会ってくるということになり、今回の展覧会になりました。
お三方とも武蔵美(武蔵野美術大学 工業デザイン学科)ですよね?
片岡:同じ時期に大学にいたんですよね。じつは永島さんと髙次さんは同級生。僕は一つ後輩なんです。
髙次:クルマの話ができるのは、この人くらいしかいなかったですね。
永島:たしかに。
髙次:普通のクルマの話は皆できるんだけど、ちょっと旧いクルマとか、マニアックなクルマというとこの人しか相手にしてくれなかった。それでよく話しをしましたね。
生粋の自動車人、Car Guyですね!
髙次:この人は特別! 自動車以外に興味がないんだから!
永島:そんなことないですよ。
髙次:ほかの趣味がないでしょう?
永島:ない、です……
髙次:ね、自動車のことばっか考えてるんですから、この人!
片岡:(爆笑)
デザイナーがやるべきことは増えていくんじゃないかと思います(片岡)
自動車人についてですが、若者のクルマ離れなんていわれますが、若い人に少なくなっているように思いますが、いかがでしょう?
永島:日本の場合ですと、例えば東京に住んでいたら僕だってクルマに乗らないかもしれないですよね。あれだけ公共交通機関がちゃんとしてて、安くてタクシーもある。それでクルマを維持するお金を考えたら、ないほうが便利という感じもします、名古屋は別かもしれませんけど。パリの郊外に住んでいたことがありますが、市内に行くときにはクルマで行ったことはないですよ。
パリでもそうなんですか?
永島:もちろんそうですよ。駐車に困るから、ないほうがいいんですよね。ですから、僕は、クルマ離れといいますが、クルマに誰もが熱中していた昔のほうが特殊な時代だったのかもしれないとそう思っています。もともとクルマというのはどうしても必要というものではなかったのではないかと。クルマというのは、実用面が大きいのですが、それ以外に趣味の対象というかいわゆるマニアックなクルマ、本当にCar Guyみたいな人たちが欲しくなるクルマ、それは残ると思うんですよね。ある意味より進化するのかもしれません。
よりおたくっぽいものが残ると?
永島:そう、そう、そう(笑)。
わくわくしますね。とはいうものの、そういうマニアの対象となるものもありますが、大部分は白物家電に近づいて行っているような気がします。
片岡:モノの歴史を考えれば、いろいろなプロダクトがそういった経緯をたどっていますね。ただ自動車の場合は、そんなに単純ではないですよ。もしかすると自動運転や電気自動車になって、外見はそれほど劇的な変化のないツルっとしたものになるのかもしれないですけど、クルマには内装がありますよね。中のデザインは本当にいろいろなことが考えられる。自動運転になったらどうなるか。そうなったときにデザインの要素はたっぷりありますよね。そこに使われる素材だったり、シートだったり、最近ではAIがつながってきてディスプレーがいっぱいついて、いろいろなところにいろんなものを映すようになってきています。そこにデザインの要素はたっぷり出てくる。デザインの種類は変わりますが、どんどんやるべきことは増えていくんじゃないかと思います。
グローバル化しても、特色が失われるわけではない(永島)
これまで自動車は、イタリア車ならイタリア車らしい感じ、フランス車、ドイツ車もそれぞれの国の特色が色濃く出ていました。それがグローバル化することで、薄まっているように感じます。どうなっていくとお考えですか?
永島:実際に会社の中に入りますとね、デザイナーというのは、ドイツの会社でもドイツ人は少数派なんです。いろんな国の人の集まりなんですよ。どのメーカーでもそうなっています。僕が最初に、約40年前にオペルに入ったときからもうヨーロッパはそういう状態でしたね。15人のデザイナーがいると、だいたい7、8カ国から来て、ほとんど国籍が重ならないのが普通のことなんです。自動車会社のデザインはそういう世界で、かなり昔からグローバル化しているんです。日本のメーカーだけが少し特殊な状態ではないかと思います。ただ、ドイツ車を考えたとき何がドイツ製品として特色を際立たせているんだろうか、あるいはイタリアでもフランスでもいいのですが、何がそう際立たせているか。外国人の眼のほうが客観的に見られるのではないかと思うんです。外国人のほうが距離を置いて客観的に見ることができる。ドイツ製品はこういうものなんだというイメージが、おそらくドイツ人本人たちよりもよく見えてるんだと思います。フランスでは、自動車業界が弱くなっていた時期があって、デザインを全部、イタリアデザインを採用している時期があるんですね。そうするとフランス人のデザイナー自身、どういうものがフランス車なのかわからなくなっているんです。僕なんかが、外部から入ってフランス車を観察して、こういうことがエッセンスなんじゃないかと絵にしますよね。そうすると、考えたこともなかったなんていわれたんです。
指摘されて初めて気がつくわけですか。
永島:ですから、果たして、ベンツやBMWがずっとドイツというプロダクトのイメージでこの先もいけるのかというのはちょっと別にして、必ずしもグローバル化したからその国の特色が失われるというのには、直結しないと思います。
イギリス車とかどうですか? ジャガーなんかを見てどんなふうに思われます?
永島:ちょっとポジションが難しいと思うのは、イギリスというのは、はっきりいえば一度、自動車産業がなくなっちゃったわけですよね、そこでアイデンティティというものがなくなったわけなんです。だからそれを再構築しない限りは、レトロに頼る以外なくなっています。ジャガーは今、それをやろうとしているわけですよ。新しいアイデンティティは何か、と模索しているんですね。ただ個人的にいうと、それほどうまくいっているとは思っていません。ほかの国のクルマといわれればそうかなと見える。フロントグリルを見なければわからないんじゃないですか。はっきりこれが新しいイギリスのスタイルだと、発見されていないと思います。いかがでしょう?
片岡:グローバル化については、その自国にいる人たちよりも、ほかの国から見ている人たちのほうが期待感が高いですよね。イギリス車はこうあって欲しいとか。
髙次:そういうことはありますよ。グローバル化しているんですけども、グローバル化すればするほど新しいアイデンティティみたいなものを求めたがります。何か特別なものが創造されない限りは、それぞれの今までの範疇から、イギリス的だとかフランス的みたいな、そういうものを欲しがるようなことになりますね。ただ、グローバル化したからといってデザインが一つになってしまう、そんなことは絶対にないですね。
片岡:ただ、企業が連携してプラットホームが共通化されたり、そうしたことでなんとなく骨格が似通ったものになっているということで、個性が薄まってしまったということはあるかもしれませんね。
人と違うことをやるというのがデザインの仕事。これは面白い!(片岡)
骨格といえば、昔はメカや構造の制約があってデザインの制約もあったと想像するのですが、現代は機械的な自由度は上がったはずで自由にデザインできるようになったと考えられます。でも、逆にすごく制約が増えたという話も耳にします、どちらなんでしょう?
永島:それは真逆ですね、どうですか?(二人に促す)
片岡:僕はもう現場を離れてだいぶたつので、そこら辺のことはあまり。
髙次:とにかくね、不利なことばっかりですよ!
昔よりも自由度が上がっている部分というのはないですか?
髙次:生産技術的にはそうなんだけど、安全基準の問題とポリューション(公害)の問題とかが厳しくなりました。少なくとも内燃機関であれば、エアクリーナーとマフラーは大きくなるしかないんですよ。どうやってボディの中に入れ込むの、みたいな話なんですよ。
永島:逆行することはありえないんですよ。安全基準は厳しくなる一方で緩くなることはありえません。同じように、CO2にしてもなんにしても、空力の要求にしても、厳しくなる一方です。僕たちデザイナーにとって一番厳しいのは、歩行者保護ですね。クルマの前半分、厳密に決まっています。煮詰めの段階にデザインが入ってクレイモデルを1ミリ動かしたら、全部計測し直しです。本当に大丈夫かどうか、調べ直さなきゃいけない。見えないですよ、1ミリなんて! でもそれぐらい厳密に制約があるんです。もうたまったもんじゃないですよ。
髙次:エンジンルームにしても、ギリギリいっぱい、そこにサービス用のスペースを設けなきゃいけなくて、年々そのスペースがたくさん必要になって……、乗り物は、全部そうですね。僕は基本的に2輪のデザインをやっていましたが、バイクはそれが全部見えてるわけですよ。どうしてくれるのみたいな話で、マフラーの化け物ができちゃうじゃないのと。最近のバイクって昔のにくらべて、おしなべてプロポーションがすごく悪いんですよね、しょうがないんですよ。
そうするとやはり限られた制約の中、知恵を絞らなきゃいけないということですね
一同:はい
髙次:でも皆、同じ条件なので頑張るしかないんですよね。
デザイナーの仕事は楽しいとおっしゃいますが、楽しいですか?
髙次:余暇は楽しいですけどね、仕事は楽しいかどうか。フリータイムでクルマをいじるのと、仕事とでは全然違いますからね。
片岡:デザインという仕事はほかの仕事にくらべたら、自動車にしてもなんにせよ、何かを生み出すことをやるわけです。これは面白いですよ。やめられない。
永島:そうですよね!
髙次:結果もよく見えるし。反応を確かめることもできるわけですし。
片岡:人と同じことをやらなくていいですからね。人と違うことをやらなければいけない。人と同じことを同じようにやるというのはあまり面白くないんだけど、人と違うことをやるというのは、これは面白い。つまらない仕事ではない、やっぱり面白い仕事。
髙次:やりがいがあるとはいえますね、簡単じゃないけど。ものとして残るという魅力もある。
永島:簡単じゃないですね(しみじみ)
手描きのスケッチに、皆、集まります。100パーセント(永島)
美術の世界の話でいえば、コンセプトが重要で実際に手で描くことが減ってきているような話を聞きます。実際のところBMWやほかの自動車メーカーではどうなのでしょうか?
永島:実際にデザイナーが紙に鉛筆で描いてるかというと、たしかにそれはかなり少ないです。ただ、要点は自分のアイデアをいかに人に伝えるかというところにあります。僕たちの使っているマーカーテクニックだって、それ以前の人たちにしてみれば、とんでもない何かであってそんな簡単なものじゃないといわれると思います、それと同じことだと思ってます。要するに、自分の考えが伝われば方法は何でもいいんです。ところが、さっきも学生さんにプレゼンテーションしたんですが、手を動かすということと頭で発想することは、何かつながっているような気がするんです、経験上。何もしないで考えているよりも、手を動かしながら見ながら考え、考えながら描き、そのほうがアイデアが出る気がするんですね。ですから、描くことはやはり意味がある。それからもう一つ、デザインのプレゼンテーションをするとします、そこにデジタルのプリントアウトの絵が20枚、1枚だけ手描きのスケッチがあったとします。すると、皆、手描きのスケッチに集まる。これはもう100パーセントそうです。単に珍しいからかもしれません、でもやっぱり何かエネルギーがあるように感じます。
片岡:学生たちもインターンシップへ行ってくるじゃないですか。そういうところでは、デジタルで描いている人が多いんですよね。そこで、手で描いて貼って来いといっているんです、手で描くほうが目立つでしょと。学生に聞くと、やっぱり手描きが目立ったといいますね。フリーハンドで絵が描ける、それができるんだったらそれを前面に出しなさいということです。うちの大学はこだわって絵を描いてますけど、ほかの大学はどんどんどんどんデジタル処理のほうへ移行していってますね。いずれ使わなければいけないんだけども、基本的に手で描けるようになってから使うほうが、道具は生きますよね。機械に支配されないようにしなきゃ。
髙次:ソフトのクセに流されるというのもありますね。抵抗しても、似てくるというのがね。人間ですから少しでも楽なほうを選択しちゃうからだと思います。そういえば、最近は自動車メーカーから説明に来てもらっても、CGでカッチリ描けといわなくなってきました。そんなのは会社に入ってからできるからそれより、アイデアはどうなの、発想は何、それをいっぱい描け、そんな感じになってきていますよ。ちょっと前まではCGできっちり描ける人の評価が高かったんですけど、最近ガラッと変わってきましたね。
つまるところは人と人(永島)
永島さんは、最初からいろいろな国の人、ものの考え方が違う人たちと仕事をしてきたわけですが、これからの社会に出て行く人は、いやおうなしにそうなっていくと思われます。うまくやっていくコツはありますか?
永島:コツなんてないと思いますよ。普通にしてるだけです。いろんな意味で日本はちょっと特殊だと思うんですよ。一度海外に出ると日本がやっぱり特殊だということがよくわかると思います。例えば、今の質問とは、ちょっとズレますが、日本で海外のニュースを見るでしょ、そうするとそれが世界だと思うわけです。政治だとか外交だとか、カリフォルニアで山火事あったと聞くとそれが世界だと思っちゃう。実際に、カリフォルニアで山火事を見ようと思ったらわざわざそこへ行って見ないと、カリフォルニアに住んでる普通の人にとってはなんの関係もないことなんです。そういうふうにニュースというのはいろいろ誤解を生むものです。イランとイラクはすごく仲が悪いということですが、僕のスタジオにはイラン人もイラク人も両方いて一緒に働いてるわけですが、なに一つトラブルはありません。人と人との交流、あるいは一緒の職場で働くことは、ニュースで見るような外交問題云々と、実際はなんの関係もないことなんです。例えば、この人はフランス人だから少し嫉妬深いかもと思ったりしますよ、面倒くさいところがあるかなと思ったりもします、でも、結局つまるところはその個人がどうなのかというところですから。
髙次:留学生もいろんな国から来て、いろいろあるんですけども、教えるのは一対一で人と人なので、あまりそういうことは考えたことないですね。海外で仕事したときのことを考えても、後から、ああ、あれはアメリカ人の特質だったのか、と思いつくことはあるんですが、総論的に人を見るということはあまりないですね、具体的に個人と仕事をするわけですから。お互いにアウトプットして議論するわけですからね。
海外で働くにあたって、語学で苦労することはなかったんですか?
永島:正直いって英語は、なかったですね。英語は、割合すぐに話せるようになりました。実際にアメリカに行ってしまえば、きっと誰でもできるようになりますよ。苦労したのはドイツ語です。まずオペルでしたが、ドイツの企業ですが会社の中、特にデザイン部門は英語が主なんですね。そうするとしゃべらないから覚えないわけですよ。
公用語が英語だったんですか?
永島:チーフも、皆、英語でしたし。それで2年ぐらいたってもあいさつぐらいしかできないんですよね。これでは駄目だと思い、語学学校へ行きました。そこで習って、やっと徐々にドイツ語はできるようになっていきました。ところが次にルノーへ移るんですが、本当に不思議なことに、フランス語は3カ月目には普通に会話できるようになったんです。ドイツ語はできなかったのにフランス語はすぐ話せるようになった。それで、僕は言葉というものには人によって相性があるということを悟ったんですね。僕にはこれが簡単だけど、この人にはこっちが簡単、といった相性があるような気がするんです、あるとしか考えられない! きっと、実際に行ってみると、なるほどと思われますよ。
仮に姪がいたとして…(永島)
この頃では、若者が海外へ出たがらない、内向き志向だといわれています。いかがなものかと思うんですけど、いかがでしょうか?
髙次:海外はつらいと思ってますよね、日本より困難なことがいっぱいあると、今より困難になると。そうした考えが根底にあるように思います。もう一つは、興味がだんだん喪失しているんです。情報が簡単に手に入るようになって、なんとなく知った気分になれるというのが蔓延してますよね。昔は、わからないから見てみたい、というのがありましたね。
永島、片岡:(うんうん、とうなずく)
髙次:今は、ピッピッと押して50パーセントくらい満足しちゃうんですよ。情報への飢餓感がないですよね。
片岡:それと、昔は海外のほうが条件がいいとか、いろんなことが良かったんでしょうね、文化も進んでるとかね。働く条件も非常に良かったと思う。今、日本と海外をくらべてどっちがいいかというと、日本のほうがいい場合も結構ありますよ。
永島:僕は個人的には海外へ出て欲しいと思うんです。でも、講義に来てくれてるような若い人たちが、ポッとドイツへ行ったりイタリアへ行ったりして安全に暮らせるかというと、それはやっぱり難しいしんじゃないかと思うんですよ。日本と海外のギャップが、あまりにも広くなり過ぎちゃってるんですよね、日本の常識のまま、海外へ行ったら危ないと思います。観光だったらいいですよ、お金を払うだけの生活だったら。海外に出て欲しいという気持ちもあるのですが、仮に自分に姪がいたとしてイタリアで働きたいなんていい出したら、ちょっと待ったほうがいいんじゃない、というと思います(笑)。
一同:えええーっ!
永島:よく考えたら、とアドバイスすると思うんですよね。勧めたいとは思うのですが、気軽にハイハイとはいえない感じがします。日本は、安全という意味では、特殊に安全な国ですよ。安全という意味が、単に犯罪者が少ないだとかじゃないんです。ずっと地面が切れるところまで、同じ人種、同じ言葉をしゃべる人がいるわけです。ヨーロッパは、違いますよね。そういう意味で安全というより安心な国なのかな、日本は。だから、僕は、出たくない人は、出なくてもいいと思うんですよ。ただ、これが世界のすべてだと思って欲しくないんです。日本は国際化してオープンになっている、とも思って欲しくない。それは間違いです。そのことを知ったうえで鎖国生活をしたいというならそれは自由です。海外とは一切かかわらないそういうチョイスもありだと思いますよ。
クルマ選びに関しても、冒険しなくなってきてるように感じます
永島:リスクを恐れるんでしょうね。それが極端になっちゃってますね。講演をやらせていただきますが、半分はデザインの話、半分はその話をしようと思ってるんですよね。日本だけがすべてではないと。聞く人に、どうとられるかはわかりませんが……。
片岡:そうはいいますが、自動車で考えれば技術的な変革が起こりつつあります。日本でも自動車に関してかなり面白いことが起きている。これから、随分変わるんじゃないかと思います。デザインなんかももっともっと変わってくると、それも日本がかなり主導するんじゃないかと思います。そういう意味ではかなり面白い時期に入ってくるんじゃないかと期待していますよ。
デザイナーの仕事は、俳優の役作りのようなもの(永島)
旧いクルマのこと、どうやってこんなに知るようなったんですか?
永島:自分でもよくわからないんですよね。興味はありましたが、特にカーグラフィック誌に描くようになってからですね。調べないと描けないじゃないですか。絵というのは、写真を写すだけじゃつまらないですからね。そのままクルマを紹介するだけではつまらないので、何か変なエピソードはないかと探します。一つを見つけると、関連を調べて、人名が出て来たらその人について調べる。すると意外な経歴があったりね、そうやってつながっているのかなと。
1枚描くのにどれぐらいの時間をかけるんですか?
永島:小さいのは2時間くらいのもありますし、すごくかかったのは1週間とかですね。
髙次:バックが凝ってるのは、時間がかかってる。
永島:水彩なので油彩ほど乾くのにも時間はいりませんし、場合によってはドライヤーを使って乾かしてもいいんですけど……。
本業でもないのに、よくここまでできるなと思います
髙次:こっちが本業なんじゃないの。やりたいことをやってるわけだし(笑)。
片岡:人生2倍に生きてますよね。二重に楽しんでいる感じがしますよ。
これを続けることで本業に役立つようなことはありました?
永島:それは、ないと思いますよ、ない気がします。ちょっと違うんですよね、仕事は、そんな気楽な世界じゃないですよ。
純粋の息抜きですか?
永島:描くことも時間は結構かかるんです。でも、描いてしまえばそれでいいわけです。会社の仕事というのは、こうしたいこれが正しいと思っても、なかなかそうならないわけです。そこが、ものすごく難しい。描くことは、大変ですけど描いてしまえばそれが印刷されるわけじゃないですか。そういう意味では息抜きですよ。
髙次:趣味的にやってるといってますけど、これは研究活動だね。僕は見ていてそう思いますよ。その通りに、クルマを描いてないんだもん! そのクルマの一番魅力的なところを表してるわけで、アーティストがモチーフに対して描いているというものとちょっと違うんですよね。
永島:たしかにそうですね。
髙次:作品の絵のほうがカッコいいじゃんていうのがたくさんありますよね。いいところだけ描いてあって、本物はそんなにカッコよくないということがあります。だから魅力的だという気もします。そのクルマのここがいいということを伝えてくれてて、まじまじとコメントを見ながら、また読みかえすと限りなく時間が潰れていってしまう。
過去のクルマのデザインをモチーフにして、新しいクルマがデザインされることがよくあります。ただ、それも一巡してきたようで、今後、どうなっていくと思われますか?
永島:そんなことはわかりませんよ!ただ日本の自動車会社とヨーロッパの自動車会社とはキャラクターがちょっと違いますよね、どっちも世の中には必要だと思います。僕は、ルノーからBMWに移りましたが、デザインするときに考えるのが、役者は一つの役から次の役へ変わるとき、自己催眠のようなことをするのじゃないのかなということです。デザイナーも同じで、例えばフェンダーラインを一本シュッとやるのであっても、動作にキャラクターの違いが自然に生じなければいけないと思うんですね。立場が変われば、BMWの線とルノーの線、自然と体から出てこないといけないと思うんです。ヨーロッパの自動車デザイナーは、各メーカーどこへ行ってもそのメーカーがどういうキャラクターなのかということを、自分で知ってなければいけないわけですよね。ところが、実際にはそれを知らない人がいっぱいいるんです。単にカッコいいデザインをする人がたくさんいるんですよ。だから自分は、自動車ファンだということでキャラクターを知ったということがあると思うし、もう一つとして、外国人だから見えるというところもあると思っています。
日本のメーカーの場合には、そういうメーカーにまつわるイメージというのは必ずしも必要なものではないと思います。あったら楽しいなと個人的には思いますよ。でも、この世の中のものすべてが主張するデザインだけじゃなくてもいいわけですから。至極便利なデザインというだけで、それはそれで完成されるものだと思います。ただヨーロッパの場合には、そういうキャラクターが必要ですね。
片岡:ブランドを作ろうということで日本のメーカーはずっと取り組んできましたけどね、表面的なことしかやってきてないですからね。その会社の歴史と文化を築き上げていこうということで、そこにブランドが生まれるわけですよね。でも、そのブランドという言葉だけが独り歩きして表面的な体面を整えようとしちゃうともうブランドの意味を履き違えてしまってわけのわからないことになってしまう。難しいですよね。
今日はありがとうございました。こうして考えてみるとトヨタのデザイナーだった木村徹さんもそうだし、武蔵美とCar Guyデザイナーの功績は大きいですね!
片岡:我々の時代は、武蔵美が多かったですけどね。あの時代に自動車のデザインをやりたい人が行く場所ってそんなになかったですからね。今は、名古屋芸大も多いですよ! 名古屋芸大からは、もう100人ほど卒業生が出てますからね!
永島、髙次:そうですね
髙次:情報がなくてね。どうしていいかわからない。武蔵美だとなんとなく佐々木達三さんがいるとかね。そんなことでちょっと自動車に近いのかなと。
永島:当時、もしも大学案内にカーデザイン科というものがあったとするなら、そこへ行ったと思います。
髙次:そういってたよね、ほかになかったですよ。それに高校生だからわからないんです、どうしていいか。今もその辺りは変わってないところもありますが。
片岡:来年は、カーデザインを志望してくれる学生もさらに増えそうだし、これからは名古屋芸大ですよ!